「癖(くせ)」 の由来
人には何かしら「くせ」がありますよね。 私は昼寝の時に足を組んで寝ます。 まるでそれはベンチに座っているかのように。 言い訳するならそれは、あまり長い時間休憩しすぎないための知恵。 無理な体勢、窮屈な形をとることで休みすぎないための工夫がなされているわけです。 ためになるな~ いやなってないですよね。 だったらしっかり寝て昼寝せずにしっかり労働すればいいわけですから。 まぁそんな理由からとっていた姿勢がいつしか心地よくなってしまったわけです。 ■「癖(くせ)」の由来 癖(くせ)とは、人が無意識のうちに、あるいは特に強く意識することなく行う習慣的な行動のこと。 広い意味では習慣の一種とされているが、必要、不必要といった判断基準もその判別に加味される。 もちろん呼吸・排泄といったものは癖とは呼ばないなんて説明の必要はないだろう。 「くせ」は自分ではあまり気づいていないというケースが多いもの。 ... »
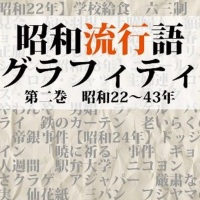
最近のコメント