「蒙古斑(もうこはん)」 の由来
蒙古斑って白人には見られないんだって。 もちろん黒人には例えあったとしてもそれと判別はつかないのだろうけど。 あ、これは差別ではありませんよ。念のため。 ■「蒙古斑(もうこはん)」の由来 蒙古斑とは・・・先天的に発生する幼児の、主に仙椎の部分の皮膚にでる薄青い灰色の母斑のこと。 所々に現れることもあるが、一つの大きなものが腰椎、仙椎、臀部、脇腹、肩に現れることが多いらしい。 通常3~5歳で消失する。 発生原因は胚の発育の段階での、真皮内のメラノサイト(蒙古斑細胞)が神経堤から表皮までの移動する間に受ける刺激からといわれている。 何もわからなかったころ、例えば江戸時代では妊娠中の性交で出血した跡と考えられていた。 確かに、男性にとっては大きな心の傷。 あのとき突かなければ娘を生まれながらの傷物にしなかったのに・・・みたいな? ドイツの内科学教授エルヴィン・フォン・ベルツが、これを「蒙古民族の... »

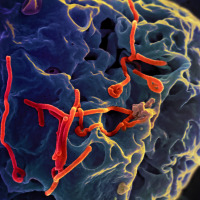


最近のコメント