「デラウェア」 の由来
世の中贅沢をいったらキリが無いものです。 私は面倒くさがりなので食べるのに手間がかかる果物が苦手です。 昔は良く食べていたブドウですが、粒の細かさからデラウェアが最近面倒。 デラウェアは糖度が20~23 度で粒の直径が10 mm~13 mm程度の赤紫色のブドウ。 でもあれだって考えてみたらわざわざ種無しに改良されているわけです。 あれだけ小さな粒で更に種があったことを想像すると・・・ 今のデラウェアにありがたやありがたやとなるわけ。 ■「デラウェア」の由来 そのデラウェア、元はアメリカ原産の自然交雑種だったのだそう。 ジベレリン処理によって果実内部の種が除去され種無しぶどうとし世の中に出てきたのだそうです。 小さい頃から食べていて身近だったあのデラウェアがアメリカ原産ということに個人的にはすごい驚きなのですが、そのカタカナの名前を考えれば確かにそうかもしれないと納得させられたり。 でも慣れ... »
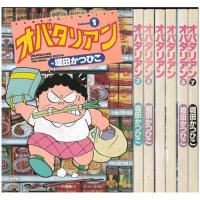
最近のコメント