「やしきたかじん」 の由来
毒舌家といえばこの人だろうか。 「やしきたかじん」 愛称は「じんちゃん」「たかじんさん」「たかじん」 四人兄弟の次男として生まれたたかじんさんは少年時代は野球に明け暮れる。 中学時代は新聞部、高校時代、生まれて初めて作曲し「コーヒーインタイム」が、NHKで採用される。 桃山学院大学経済学部に進学し新聞記者を目指していたがある理由から父と対立し勘当、そのまま中退にいたる。 その理由とはなんとNHK嫌い。 公共放送のやり方がどうにもお気に召さなかったらしい。 その後、龍谷大学経済学部へ入学するがやはり中退。 京都祇園のクラブでギターとピアノの弾き語りをしながら歌手を目指す。 そうなのだ、普段のしゃべる時のだみ声の地声と、歌うときの高く澄んだ甘い歌声とのギャップがあまりにも大きいため、関西以外ではたかじんさんが歌手であるという認識が薄い。 もちろん私も知らなかった。 余談だが、歌手でありながら日... »
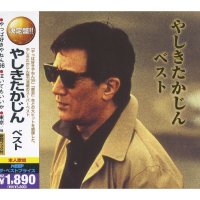
最近のコメント